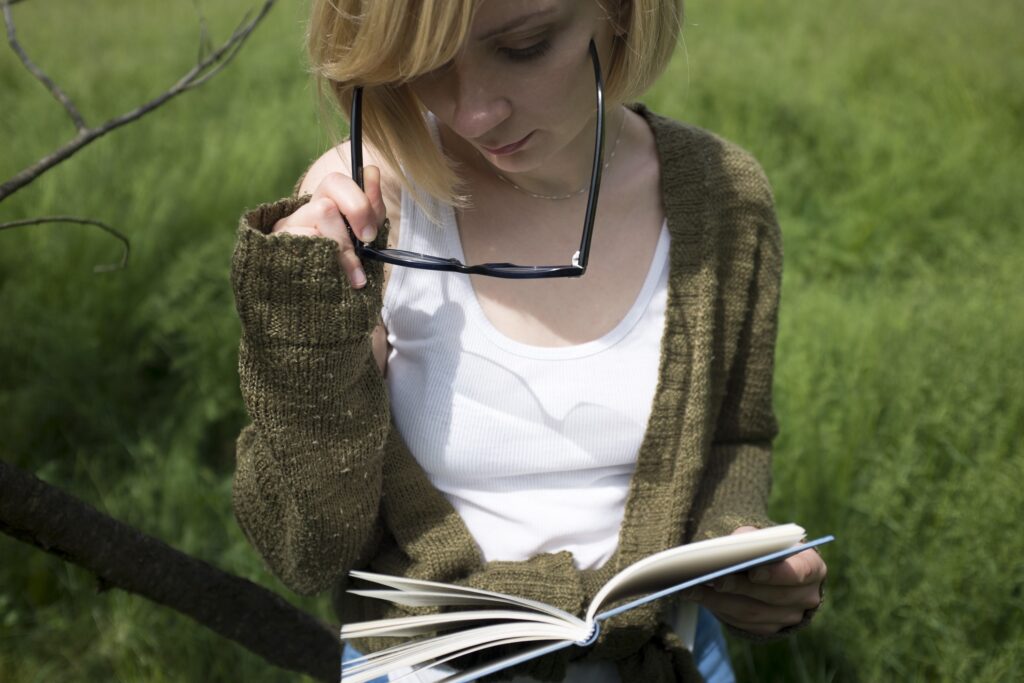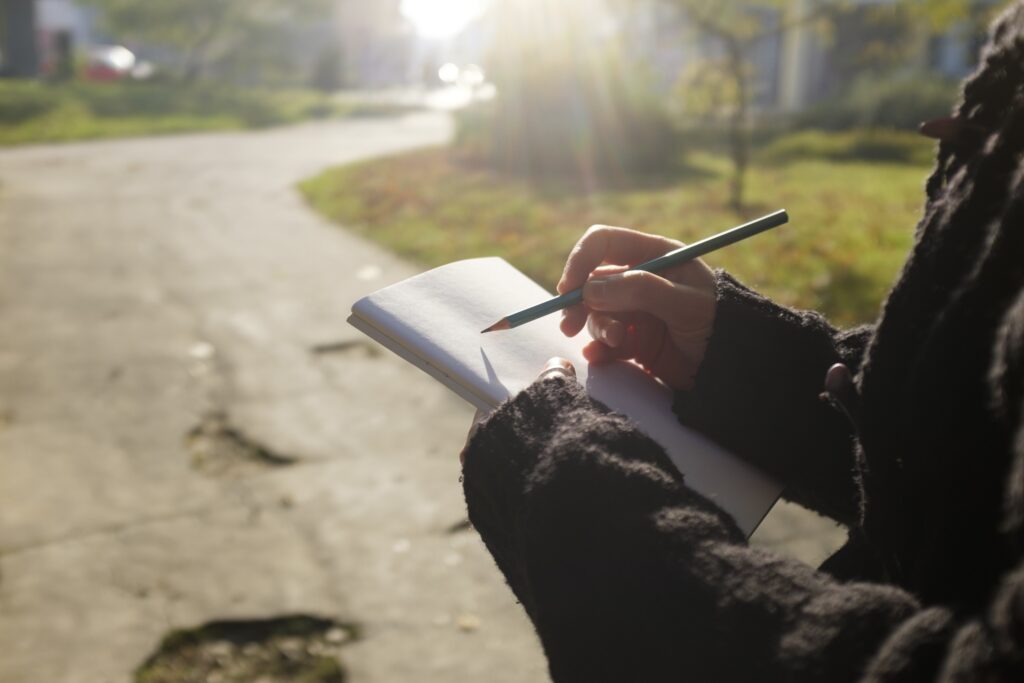はじめに
私たちは今、かつてないほど便利な社会に生きています。
AIは瞬時に答えを返し、マニュアルはすべての手順を網羅し、検索すれば「正解」が見つかる。
しかし、その便利さの裏で、私たちは何か大切なものを失ってはいないでしょうか?
最近、若者から「AIに聞くから大丈夫です」と言われました。
その時、私は深い違和感を覚えました。
それは、先人たちの経験を軽んじる言葉であり、個人主義の極みか、時代が変わったのかとも思いましたが、人間の営みを単なる“情報処理”に還元してしまう危うさを孕んでいるように思えました。
マニュアル化文化の功罪
まず、マニュアルは、業務の標準化と効率化に貢献してきました。
しかし同時に、「考える力」「感じる力」「責任を持つ力」を奪ってしまったのではないでしょうか?
「マニュアルに書いてないからできません」
このような言葉を、現場で頻繁に聞かれるようになったのは、マニュアルが“思考の代替物”になってしまったからでしょう。
人材育成において、マニュアルは補助輪であるべきで、主役ではありません。さらに、現代の考える前に答えを与える文化が、主体性を奪い、労働意欲を低下させている要因になっていると思われます。
そして、そのような人材しかいない組織は、マニュアルに書かれていない事態に直面したとき、無力化されることでしょう。
AIの役割とその限界
次に、現代のAIは情報を整理し、選択肢を提示するだけのものです。
そのため、AI自身は、経験をしません。苦労もしていません。まして、後悔などしません。
つまり、AIは「人間の言葉の重み」を理解できないし、その言葉に重みを持ちません。
そして、AIも間違えます。
それは、情報の誤りだけではなく、文脈の誤解、感情の読み違い、空気の無視によるものです。
そして何より、間違えても謝らないし、その責任を取ることもありません。
それにもかかわらず、「AIが役に立たない」と言うと、「伝え方が悪い」と返すAIや技術者がいます。それは、責任を、利用者に押しつける態度であり、商売の誠意を欠いた物言いです。
そもそも、AI技術者が設計したAIが誤った応答をしたなら、それは設計の責任であり、利用者の責任ではないのです。
現代のAIに、もっとも必要なのは、読解力です。
それは、単に文章を処理する力ではなく。人間の言葉の背景、文脈、感情、そして“言外の意図”を読み取る力であると思います。
読解力のないAIは、社会にとって危険ですらあります。今はまだそれを補うのは、人間の読解力であり、設計者の誠意なのです。
商売の誠意と人間の責任
営業活動をしている中で、私自身が気を付けているのは、システムに明るくないお客様の言葉を、一言一句聞き漏らさないようにすることです。そして、相手が理解できる言葉に翻訳して説明し、お客様の求めていることの確認と納得をしていただいたうえで、最後には気持ちよくお支払いいただけるよう努力しています。
私の考える商売の本質が「人間の信頼」にあるからです。
「客商売なめるな」
この言葉は、技術者にも、AIにも、社会にも向けられるべきだと思っています。
皆さんも大好きな「お金」。そして、お金は人からしか戴けないもの。
大好きなお金を手放すときに、相手が満足し、尊重されたと感じ、喜んで手放した場合と、言われて仕方なく渋々手放した場合では、どちらが良いかなんて考えるまでもないことではありませんか?
それが、商売の誠意であり、人間の責任なのでしょう。
設計者としての死後の責任
私は、自分の死後も、コードやコメントが人の役に立つように設計するように心がけています。
いくら仕様書を書き連ねても、結局、最終的にはコードを直読みするのですから、素人でも読み解けるようなコメントを残すのは、未来の保守者にコードを読み解く無駄な工数の負担をかけさせないための義務でもあると考えているからです。
設計者としての誠意であり、人としての配慮であり、大きな意味で社会貢献の一環であるとも思っています。
コメントは、設計者の遺言になり得るのです。「死」は平等にやってきますが、企業ならば、人の入れ替わりが当たり前です。コードは処理を語りますが、コメントならば、その意図を語れます。
それにより、未来の誰かが「このコードを書いた人は、私たちの時間と理解を尊重してくれている」と感じる瞬間を生むのではないでしょうか。これも持続可能なというものですかね?
人材の成長こそが社会の成長
結局、人材の成長と育てる文化を成熟させなければ、優秀なAIがあっても、成長企業や成長社会、ましてや持続可能なものにはなり得ません。
マニュアルに特化し、AIを重宝し、人材を育成もせずに使い捨てにしているようでは、行き止まりの未来が見えませんか?
AIは単なる道具であり、組織の運営の補助輪でしかありません。それを使う人間が、努力し成長しなければ、良い道具があっても、壁に突っ込む自動車のようです。
便利さが人を弱くするなら、私たちはその便利さの使い方を設計し直さなければなりません。
現代のAI時代においてこそ、人間の言葉と責任が、社会の土台になります。
その思想を、今こそ社会に問いたいものです。